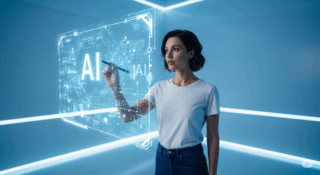基本の4点セット
AIに何かを作成してもらう時、最低でも以下の「基本の4点セット」を伝えるだけで、仕上がりが格段に良くなります。
1.【誰が】 – 書き手はどんな人?
あなたがどんな立場の人になりきってAIに書いてほしいのかを伝えます。これによって、文章のトーンや使う言葉の選び方が決まります。
- (例)
経験豊富なベテラン看護師最近プログラミングを始めたばかりの大学生5歳の娘を育てる母親
2.【誰に】 – 読み手はどんな人?
この記事や文章を、最終的に誰に読んでほしいのかを伝えます。相手に合わせて、AIが言葉の難しさや内容の深さを調整してくれます。
- (例)
ITの知識がまったくない高齢者の方々就職活動を控えた大学生仕事で忙しい30代のビジネスパーソン
3.【何を】 – いちばん伝えたいことは何?
文章のテーマや結論、絶対に伝えたい核心部分を明確にします。これがブレると、AIが作る文章もぼんやりしてしまいます。
- (例)
新発売するお菓子の、これまでにないサクサク食感の魅力地域のお祭りが、今年はオンラインでも参加できるという告知地球温暖化が私たちの生活に与える具体的な影響
4.【どんなふうに】 – 文体・トーン・形式は?
文章全体の雰囲気や見た目を指定します。箇条書き、ブログ記事、メールなど、最終的なアウトプットの形を伝えると、AIがその形式で作成してくれます。
- (例)
- 文体:
親しみやすい話し言葉で丁寧なですます調で論文のような、だである調で - トーン:
読者を励ますような、温かいトーンで専門家としての、客観的で冷静なトーンで - 形式:
箇条書きで3つにまとめてブログ記事として作成してSNS投稿用に150文字以内で
- 文体:
もう一歩踏み込む!仕上がりを左右する追加要素
基本の4点セットに加えて、以下の2点を加えると、さらにあなたの理想に近い文章が出来上がります。
5.【目的・ゴール】 – 読者にどうなってほしい?
その文章を読んだ人に、最終的にどんな気持ちになったり、どんな行動をとってほしかったりするのかを伝えます。
- (例)
商品の購入を検討してほしい内容に共感し、安心した気持ちになってほしいサービスの会員登録をしてほしい
6.【条件・制約】 – ルールや、必ず守ってほしいことは?
文字数や、必ず含めてほしいキーワード、逆に使ってほしくない言葉などを指定します。
- (例)
全体で800字程度で専門用語は使わずに、中学生にも分かるように説明して「簡単」「誰でもできる」というキーワードを必ず入れて
具体例で見てみよう!
× 悪い例(これだとAIも困ってしまう…) AIについてブログ記事を書いて。
◎ 良い例(これならAIも腕がなる!) 以下の要件でブログ記事を作成してください。
- 【誰が】
最近AIの便利さに気づいた50代の主婦ブロガー - 【誰に】
AIに興味はあるけど、難しそうだと感じている同世代の女性 - 【何を】
生成AIが私たちの日常生活(料理や調べものなど)で、実はスマホで簡単に使える相棒になること - 【どんなふうに】
読者に語りかけるような、親しみやすい「ですます調」のブログ記事形式で。 - 【目的・ゴール】
読者が「私にもできそう!」と感じて、AIを試してみるきっかけを作ること。 - 【条件・制約】
文字数は1500字程度。専門用語は避け、具体的な使い方を3つほど紹介してください。
もっと気軽に!「4点セット」を省略できるケース
いつも先ほどのような「発注書」をしっかり書かなければいけない、というわけではありません。AIの使い方に慣れてくると、もっと手軽な「便利な文房具」のような使い方もできます。
こんな時は「要件だけ」でOK!
1. 文章の要約・箇条書き化 長いニュース記事やメールの内容を、手早く把握したい時に便利です。
- (例)
以下のニュース記事を、3つのポイントで要約して。[ここに記事のURLや文章を貼り付け]このメールの内容を、箇条書きで分かりやすく整理して。[ここにメールの文章を貼り付け]
2. アイデア出し(ブレインストーミング) 自分一人では思いつかないようなアイデアのタネが欲しい時、AIは優秀な壁打ち相手になります。
- (例)
小学生の娘が喜びそうな、週末のお出かけ先のアイデアを10個出して。会社の歓送迎会で使える、面白いアイスブレイクのネタを5つ考えて。「夏の涼」を感じるブログのタイトル案を、違う切り口で10個提案して。
3. 文章の変換・校正 文章のトーンを変えたり、誤字脱字をチェックしてもらったりする作業です。
- (例)
この文章、もっと丁寧な敬語表現に書き換えてください。次の文章を、フレンドリーで親しみやすい表現に変えて。以下の文章で、誤字脱字や不自然な日本語がないかチェックして。
4. 翻訳 言わずと知れた便利な使い方です。単語だけでなく、文脈を汲んだ自然な翻訳をお願いできます。
- (例)
「大変恐縮ですが、会議を欠席させていただきます。」を、自然なビジネス英語に翻訳して。この英語のレビューサイトに書いてある内容を、日本語で要約して教えて。
★★ amanatsuからのワンポイント・アドバイス ★★
AIは、あなたが頭の中で考えていることを察してくれるエスパーではありません。「これくらい言わなくても分かるかな?」と思わずに、「ちょっと丁寧すぎるかな?」と感じるくらい具体的に、たくさんの情報を伝えるのが成功の秘訣です。
しっかりした文章を作ってほしい時は「基本の4点セット+α」を意識する。 要約やアイデア出しなど、単純な作業を手伝ってほしい時は「やってほしいことだけ」を伝える。
このように、目的によってAIへの「お願いの仕方」を使い分けるのが、AIと上手に付き合うコツです。 あなたがAIを「文章家」として雇うのか、それとも「便利な文房具」として使うのか。その時々で立場を変えてあげるイメージですね。
この使い分けができるようになると、AIはもっとあなたの生活に寄り添った、強力なサポーターになりますよ!
AIと対話しながら、一緒に理想の文章を作り上げていくパートナーのようなイメージで、ぜひ色々とお願いしてみてくださいね!
もっと詳しくAIを学ぶなら七里信一氏の開催するChat-GPT活用セミナーがおすすめです下のリンクからぜひ見てみてくださいね。
この記事を書いた人 Wrote this article
amanatsu 女性
こんにちは、amanatsuと申します。母の介護をしながら夫と3人で暮らしている50代の主婦です。 いろいろなことに挑戦して、最近は生成AIの学校「飛翔」でAIのあれこれを学びプロンプトエンジニアの認定をいただきました。日々の健康や学びで得た「AIでちょっと便利になること」などをお伝えしていきます。